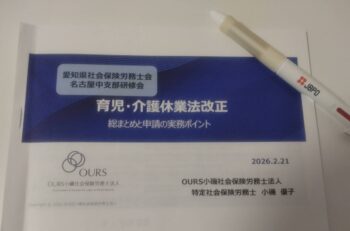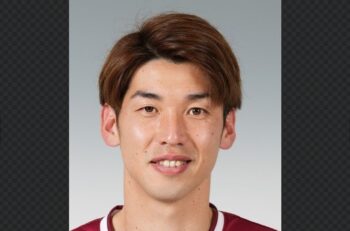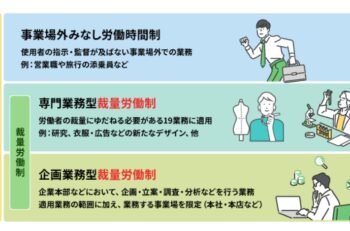従業員が10名以下で就業規則がない・・・でも従業員へ労働条件通知書を書かなければ・・・
こんな相談を受けました。
「まだ社員は10名以下で、就業規則を作っていません。今までは特に不具合もなかったのですが、今回長期雇用者を雇うこととなりました。ただ、労働条件通知書(雇用契約書)を交付しなければならず、ひな形などを見ていますが、退職や解雇など、書かれているのを見ると、「就業規則第〇条の記載による・・・」という表記が多く、就業規則がない会社の場合、どう対応すればよいか・・・」
2点、注意する所があります。
1,労働条件通知書は従業員を雇用するときに必ず作成し、従業員に交付しなければいけません。また、絶対的明示事項と言われ、記載しなければならない事項も法令で規定されており、「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」もその一つです。また、労働条件通知書は労働者が一人であっても交付が必要です。
(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項)
2,常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第89条)
労働者が10人未満であっても、ルールを明確化するためにも就業規則を作成することが望ましいとされています。ですから、今回を機に就業規則を整えられてもいいですね。
ただ、すぐに就業規則を作成、というわけにはいかないかもしれません。
そのような場合、退職等に関する事項を先に定め、別紙に記載する形式で労働条件通知書と合わせて交付する方法もあります。
就業規則のひな型を参考に、退職等に関する事項を定めます。ただし、ひな型に記載されている項目をそのまま使用するのではなく、過不足がないか、文言を手直しする必要がないか、十分検討する必要があります。また、これから作成する就業規則と齟齬が生じることがないよう、注意して下さい。
ただ、後々を考えると、一気に就業規則の作成をした方が賢明です。
社労士にすべて投げるのも手でしょう。
社労士は問題が起こる前に社内の人事・労務を整える専門家です。いわゆる、予防措置は社労士です。
問題が起こってしまえば弁護士の登場ですが、事前にそうならない対策は不可欠です。だから社労士を頼っていただいていいのです。